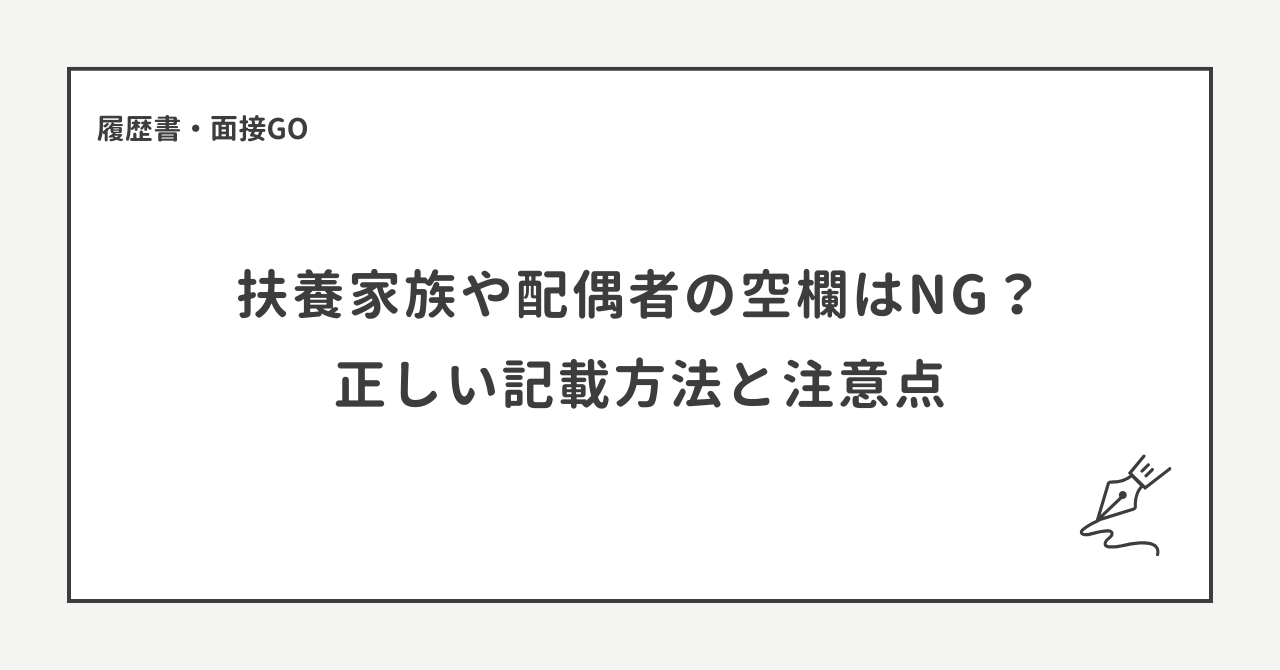履歴書を書くとき、扶養家族や配偶者の欄を見て「これ、空欄でもいいのかな?」と迷ってしまうことはありませんか。実は、この欄を適当に扱ってしまうと、思わぬトラブルを招くことがあります。
企業にとって扶養家族の情報は、給与計算や社会保険の手続きに直接関わる重要なデータです。正しく記入しないと、入社後に面倒な手続きが発生したり、場合によっては信頼を失うことにもつながります。
この記事では、扶養家族や配偶者欄の正しい書き方を、具体的な例文とともに詳しく解説していきます。あなたの状況に合わせた記入方法が必ず見つかるはずです。
扶養家族や配偶者欄を空欄にするとNGな理由は?
履歴書の扶養家族・配偶者欄は、単なる形式的な項目ではありません。企業にとっては、採用後の各種手続きを円滑に進めるための重要な情報源となっています。
空欄のまま提出してしまうと、後々困ったことになるケースが多いのです。まずは、なぜこの欄が重要なのかを理解しておきましょう。
企業が扶養家族情報を必要とする3つの理由
企業が扶養家族の情報を求める理由は、主に以下の3つです。
1つ目は、給与計算での扶養控除の適用です。扶養家族がいる場合、所得税や住民税の計算で扶養控除が適用されます。これにより、手取り給与が変わってくるため、正確な情報が必要になります。
2つ目は、社会保険の加入手続きです。健康保険では、扶養家族を被扶養者として加入させる手続きが必要です。この際、扶養家族の人数や続柄、収入状況などの詳細な情報が求められます。
3つ目は、家族手当などの福利厚生の適用判断です。多くの企業では、配偶者や子どもに対して家族手当を支給しています。支給対象者を正確に把握するために、家族構成の情報が不可欠となります。
空欄のまま提出した場合のリスクとは
履歴書の扶養家族欄を空欄にして提出すると、いくつかのリスクが生じます。
最も多いのが、入社後の手続きが遅れるケースです。扶養家族がいるにも関わらず空欄にしていると、社会保険の加入手続きや給与計算でやり直しが発生します。これにより、正しい給与の支給が遅れたり、健康保険証の発行に時間がかかったりします。
また、企業の人事担当者からの信頼を失う可能性もあります。重要な情報を正確に記載していないと「この人は注意深さに欠ける」と判断される恐れがあります。特に事務職や経理職など、正確性が求められる職種では、マイナス評価につながることもあります。
さらに深刻なのが、後から修正が必要になった場合の手間です。税務署への扶養控除申告書や健康保険組合への被扶養者届など、複数の書類を修正・再提出する必要が生じます。
法的な手続きで必要になる場面を紹介
扶養家族の情報は、法的な手続きでも重要な役割を果たします。
税務関係では、年末調整の際に扶養控除等申告書への記載が必要です。この書類は税務署にも提出されるため、履歴書の情報と整合性が取れていることが重要になります。
労働保険の手続きでも、家族の情報が必要になる場合があります。特に労災保険では、被災した際の給付金計算で扶養家族の人数が影響することがあります。
また、退職時の手続きでも扶養家族の情報は重要です。失業保険の給付を受ける際、扶養家族がいる場合は給付日数や金額が変わることがあります。入社時から正確な情報を管理しておくことで、これらの手続きもスムーズに進みます。
履歴書の扶養家族・配偶者欄の正しい記載方法はこれ!
扶養家族・配偶者欄の正しい記載方法を知っておけば、迷うことなく履歴書を完成させることができます。ここでは、具体的な書き方のポイントを詳しく説明していきます。
間違えやすいポイントもあわせて解説するので、しっかりと確認してください。
扶養家族数の書き方と数え方のポイント
扶養家族の数え方には、明確なルールがあります。まず理解しておきたいのは「配偶者を除く扶養家族の人数」を記載するということです。
扶養家族として数えるのは、あなたの収入で生活している家族です。具体的には、年収が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)で、あなたと生計を一にしている家族が対象になります。
一般的に扶養家族に含まれるのは以下のような人たちです。子ども(大学生など働いていない場合)、両親(年金受給額が少ない場合)、祖父母(同居しており収入が少ない場合)、兄弟姉妹(学生など働いていない場合)などが該当します。
記載する際は、単純に人数だけを書くのが基本です。
扶養家族:2人年齢や続柄を詳しく書く必要がある場合は、履歴書の形式に従って記載しましょう。多くの履歴書では、人数のみの記載で十分です。
配偶者の有無はどう判断する?
配偶者の有無は、法的な婚姻関係があるかどうかで判断します。役所に婚姻届を提出して正式に結婚している場合は「有」、独身の場合は「無」と記載します。
注意したいのは、同棲や婚約中の場合です。まだ婚姻届を提出していない状態では、配偶者の有無は「無」となります。たとえ長期間一緒に住んでいても、法的な婚姻関係がなければ配偶者とは認められません。
内縁関係や事実婚の場合は、やや複雑になります。一般的には「無」と記載しますが、企業によっては事実婚を配偶者として扱う場合もあります。迷った場合は、面接時に確認するか、備考欄に簡潔に状況を記載しておくと良いでしょう。
離婚や死別の場合も「無」と記載します。過去の婚姻歴について詳しく書く必要はありません。現在の状況のみを正確に記載すれば十分です。
配偶者の扶養義務の正しい記入方法
配偶者の扶養義務とは、あなたが配偶者を経済的に支えているかどうかということです。これは配偶者の収入状況によって決まります。
配偶者の年収が130万円未満の場合、一般的には扶養義務「有」となります。専業主婦(主夫)やパートタイムで働いている配偶者が該当します。
一方、配偶者がフルタイムで働いており、年収が130万円以上ある場合は扶養義務「無」となります。共働き夫婦の多くがこのケースに当てはまります。
記載方法は以下のようになります。
配偶者:有 扶養義務:有
配偶者:有 扶養義務:無
配偶者:無配偶者がいない場合は、扶養義務の欄も自動的に「無」となります。間違えて空欄にしないよう注意しましょう。
ケース別で見る扶養家族・配偶者欄の記入例を紹介
実際の記入例を見ることで、より具体的な書き方を理解できます。ここでは、よくあるケース別に記入例を紹介していきます。
あなたの状況に近いケースを見つけて、参考にしてください。
独身の場合の記入例
独身の方の場合、配偶者は当然いないので「無」と記載します。扶養家族についても、多くの場合は「0人」となるでしょう。
配偶者:無
扶養家族:0人ただし、独身でも扶養家族がいるケースがあります。例えば、両親と同居しており、両親の収入が少ない場合は扶養家族として数えることがあります。
両親を扶養している独身の方の場合は以下のようになります。
配偶者:無
扶養家族:2人学生時代から一人暮らしを続けており、実家の両親とは経済的に独立している場合は、同居していても扶養家族には含めません。扶養の判断は「生計を一にしているかどうか」がポイントになります。
既婚で配偶者を扶養している場合
専業主婦(主夫)の配偶者がいる場合や、配偶者の収入が少ない場合は、以下のように記載します。
配偶者:有 扶養義務:有
扶養家族:0人子どもがいる場合は、子どもの人数を扶養家族として記載します。
配偶者:有 扶養義務:有
扶養家族:2人この例では、配偶者のほかに子どもが2人いることを示しています。配偶者は扶養家族の人数には含めないことに注意してください。
配偶者の両親と同居しており、両親も扶養している場合は、その人数も含めて記載します。
配偶者:有 扶養義務:有
扶養家族:4人この場合、子ども2人と配偶者の両親2人を合わせて4人となります。
既婚で夫婦共働きの場合
夫婦ともにフルタイムで働いている場合、一般的には互いに扶養関係はありません。
配偶者:有 扶養義務:無
扶養家族:0人子どもがいる場合は、どちらか一方の扶養に入れることになります。通常は収入の多い方の扶養に入れるため、あなたが扶養者となる場合は以下のようになります。
配偶者:有 扶養義務:無
扶養家族:1人逆に、配偶者の扶養に子どもを入れる場合は、扶養家族は0人となります。このような場合は、入社後に詳細を確認されることが多いので、面接時に説明できるよう準備しておきましょう。
独身で親を扶養している場合
独身でも、両親や祖父母を扶養しているケースがあります。特に、親の年金収入が少ない場合や、病気で働けない場合などが該当します。
配偶者:無
扶養家族:2人この例では、両親2人を扶養している状況を示しています。同居している場合はもちろん、離れて住んでいても定期的に生活費を送金している場合は扶養家族として認められることがあります。
祖父母も含めて扶養している場合は、その人数を合わせて記載します。
配偶者:無
扶養家族:4人ただし、扶養の認定には収入要件があるため、親や祖父母の年金額や他の収入を確認してから記載することが大切です。
内縁関係・事実婚の場合の書き方
内縁関係や事実婚の場合、法的な婚姻関係がないため、基本的には配偶者の有無は「無」となります。
配偶者:無
扶養家族:1人この場合、内縁の配偶者を扶養家族として記載することがあります。ただし、企業によって取り扱いが異なるため、面接時に確認することをおすすめします。
子どもがいる場合は、認知の有無に関わらず扶養家族として数えることができます。
配偶者:無
扶養家族:2人内縁関係について詳しく説明が必要な場合は、備考欄を活用するか、面接時に説明する準備をしておきましょう。企業側も適切に対応してくれるはずです。
扶養家族・配偶者欄で間違いやすい注意点は?
扶養家族・配偶者欄の記入では、多くの人が同じような間違いをしてしまいます。ここでは、特に注意すべきポイントを詳しく解説していきます。
事前に知っておくことで、ミスを防ぐことができますよ。
「配偶者を除く」の意味を理解しよう
履歴書でよく見る「配偶者を除く扶養家族」という表現は、多くの人が混乱するポイントです。これは、扶養家族の人数を数える際に、配偶者は含めないということを意味しています。
例えば、専業主婦の妻と子ども2人がいる場合を考えてみましょう。家族は合計3人いますが、扶養家族として記載するのは子ども2人のみです。妻は「配偶者」として別に記載するため、扶養家族の人数には含めません。
この仕組みを理解していないと、「家族3人だから扶養家族3人」と間違って記載してしまいます。正しくは以下のようになります。
配偶者:有 扶養義務:有
扶養家族:2人「配偶者を除く」という言葉を見たら、配偶者以外の扶養している家族の人数を数えることを思い出してください。
年収130万円の基準で判断を間違うケース
扶養の判断で最も重要な基準が「年収130万円」です。しかし、この基準を間違って理解している人が少なくありません。
よくある間違いは、130万円を「手取り額」で考えてしまうことです。正しくは「総収入」で判断します。つまり、税金や社会保険料を引く前の金額が130万円未満かどうかで判断します。
また、パートで働いている配偶者の場合、月収で考えると約10万8千円が目安になります。この金額を超える月が続くと、年収130万円を超える可能性が高くなります。
さらに注意が必要なのは、将来の収入見込みで判断することです。現在は130万円未満でも、昇給や勤務時間の増加で130万円を超える見込みがある場合は、扶養から外れることになります。
失業保険や傷病手当金などの給付金も収入に含まれるため、これらを受給している間は扶養から外れる場合があります。複雑なケースでは、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
子どもの年齢・収入状況での判断ミス
子どもを扶養家族として数える際も、年齢や収入状況で判断を間違えやすいポイントがあります。
最も多い間違いは、大学生の子どもを自動的に扶養家族に含めてしまうことです。大学生でもアルバイトで年収130万円以上稼いでいる場合は、扶養家族には含まれません。
また、社会人になった子どもでも、病気やケガで働けず、親が経済的に支援している場合は扶養家族として認められることがあります。単純に年齢で判断するのではなく、実際の収入状況を確認することが大切です。
高校生以下の子どもは、通常はアルバイト収入があっても扶養家族として扱われます。ただし、子役やモデルなど特殊な職業で高収入を得ている場合は例外となることもあります。
さらに、離婚した元配偶者との間の子どもについても注意が必要です。親権がなくても、実際に養育費を支払って経済的に支援している場合は、扶養家族として認められる場合があります。
同居していても扶養していない場合の対処法
家族と同居していても、経済的に独立している場合は扶養家族には含まれません。この判断を間違えるケースが時々見られます。
例えば、結婚した子どもが親と同居している場合を考えてみましょう。子どもが独立して働いており、家計も別にしている場合は、同居していても扶養家族ではありません。逆に、家事や子育てを手伝ってもらう代わりに生活費の一部を負担している場合は、扶養関係があると判断される場合もあります。
このような複雑なケースでは、実際の生活実態に基づいて判断することが重要です。「誰が誰の生活費を負担しているか」を明確にして記載しましょう。
また、同居の祖父母についても注意が必要です。年金収入がある場合、その金額によって扶養の判断が変わります。遺族年金や障害年金は非課税所得ですが、扶養の判定では収入として扱われる場合があります。
迷った場合は、入社後に人事担当者と相談して正確な情報を伝えることをおすすめします。最初から正確に記載しようとして悩むよりも、概算で記載して後から調整する方が現実的です。
扶養家族として認められる条件と定義を解説
扶養家族の認定には、明確な条件があります。ここでは、健康保険と税法の違いも含めて、詳しく解説していきます。
正しい条件を理解することで、迷わずに記載できるようになります。
健康保険上の扶養家族の条件とは
健康保険における扶養家族(被扶養者)の認定には、いくつかの条件があります。まず重要なのは、被保険者(あなた)との続柄です。
配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属は、同居していなくても扶養家族として認められます。一方、叔父叔母、甥姪などの3親等以内の親族は、同居していることが条件となります。
収入条件については、年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることが基本です。さらに、被保険者の年収の2分の1未満であることも求められます。
例えば、あなたの年収が300万円の場合、扶養家族の年収は150万円未満である必要があります。この場合、130万円という基準よりも厳しい条件が適用されることになります。
同居が必要な場合の「同居」とは、住民票上の住所が同じであることを指します。一時的な別居(出張、入院など)は同居として扱われますが、長期間の別居は認められません。
健康保険組合によっては、独自の基準を設けている場合もあります。入社後に詳細な確認が行われるため、履歴書の段階では概算で記載しておけば問題ありません。
税法上の扶養家族との違いは?
税法上の扶養控除と健康保険の被扶養者では、条件が異なります。この違いを理解しておくことで、混乱を避けることができます。
税法上の扶養控除では、年収103万円以下という基準があります。これは健康保険の130万円よりも厳しい条件です。また、配偶者については別途「配偶者控除」「配偶者特別控除」という制度があり、年収201万円以下まで段階的に控除が適用されます。
税法では同居の要件も健康保険より緩やかで、生計を一にしていれば扶養控除の対象となります。別居していても仕送りを継続的に行っている場合は、扶養控除が認められます。
年齢制限も異なります。健康保険では年齢制限がありませんが、税法上の扶養控除は16歳以上が対象です。15歳以下の子どもは扶養控除の対象にはなりませんが、児童手当の対象となります。
履歴書の扶養家族欄では、通常は健康保険の基準で記載することが多いです。ただし、企業によっては税法上の扶養も考慮して確認される場合があるため、両方の基準を理解しておくと良いでしょう。
75歳以上の家族は扶養に含まれない理由
75歳以上の家族については、健康保険の扶養家族に含むことができません。これは後期高齢者医療制度があるためです。
75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。この制度は独立した医療保険制度であり、家族の健康保険の扶養に入ることはできません。
ただし、税法上の扶養控除については年齢制限がないため、75歳以上の家族でも条件を満たせば扶養控除の対象となります。収入が少ない親や祖父母を経済的に支援している場合は、扶養控除を受けることができます。
履歴書の記載では、このような複雑な制度の違いまで考慮する必要はありません。実際の扶養状況に基づいて記載し、詳細は入社後に確認してもらえば十分です。
例えば、75歳の父親を経済的に支援している場合は、以下のように記載できます。
扶養家族:1人備考欄がある場合は「税法上の扶養のみ」などと記載しておくと、より正確な情報を伝えることができます。
企業の人事担当者も、このような制度の違いは理解しているため、過度に心配する必要はありません。正直に現在の状況を記載することが最も重要です。
まとめ
履歴書の扶養家族・配偶者欄は、単なる形式的な項目ではなく、入社後の各種手続きに直結する重要な情報です。空欄にしてしまうと、給与計算や社会保険の手続きで問題が生じる可能性があります。
記載の基本ルールは、配偶者は別項目として記載し、扶養家族は「配偶者を除く」人数を記入することです。扶養の判断は年収130万円未満という基準が基本となりますが、健康保険と税法では条件が異なることも理解しておきましょう。
独身、既婚、共働きなど、それぞれの状況に応じた記載例を参考にして、あなたの実情に合った記載を行ってください。迷った場合は、入社後に人事担当者と相談して正確な情報を伝えることで、適切に対応してもらえます。
正しい記載により、スムーズな入社手続きと信頼関係の構築につなげていきましょう。